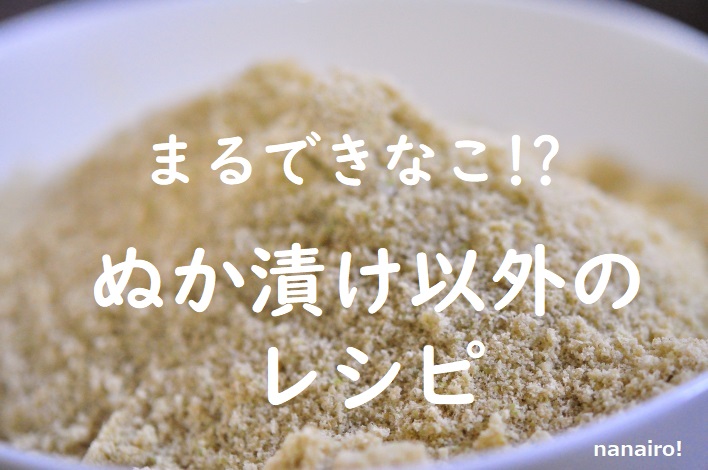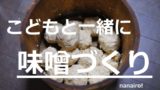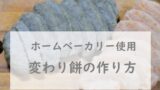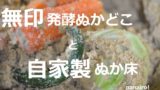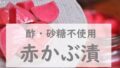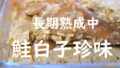こんにちは。
都内で発酵ワークショップnanairo!を主宰しています、マキ太です。
はじめての方は、こちらもどうぞ。
自家製の発酵食品を使った料理は、Twitterでほぼ毎日更新中。
週末、
朝6時前に起きて、豆を煮始めます。

昨日は、今シーズン2回目の親子で作る「味噌作りワークショップ」でした。
はじめの30分は、アクを取るのに大忙し!

朝食は、3口コンロが使えないので、
オーブンでパンを焼くことが多いです。
昨日の夜作って、冷蔵庫で低温発酵させておいたジンジャーシロップ入りのパン生地。
1番に起きてきた長女に、形成をお願いし、

私はアク取りに専念!
いつの間にか末っ子も加わり、
まわりにきなこ…ではなく、「ぬか」をまぶします。

オーブンで焼くと…

ほぉ~♪
香ばしい香りの、焼きたてジンジャーパンです (=゚ω゚)ノ
さて!
ワークショップに参加するが初めての方の中にも、
味噌作りの経験のある方は多くいらっしゃいます。

ー味噌は何で蓋をするか?
この話題1つでも、
「ラップ」「塩」「ワサビ」「和紙」など、どんどん話が広がります。
これが正解!という答えがないのが、発酵食のいいところでもあります。

そんな話をしながら作る味噌、
今回は麦味噌と玄米味噌を5kgずつ作りました。

ー出来上がったら、ちょっと交換してみない?
そんな素敵な提案もされていました。

ワークショップがきっかけになり、発酵好きの輪が広がっていくのは
とても嬉しいです♪
子供と一緒に作る時、あると便利なアイテムも紹介しています。
ぬかをアルファー化!?旨味と保存性をアップさせる方法
ワークショップでは、途中休憩を兼ねて、
おやつなどをお出ししています。
今回は、つきたてのお餅でした。

皇居の水田でも育てられていて、宮中祭祀(きゅうちゅうさいし)でも使われている
マンゲツモチという品種で作りました。
この「マンゲツモチ」は、病気に弱いため、米作りが難しい品種と言われているそうで、
あまり、市場には流通しないレアな品種だそうです。
そんな希少品種の「マンゲツモチ」。
味のほうは、甘味が強く粘りが強いので、お餅を食べている感じがスゴイです。
あぁ。。。 早く杵(キネ)と臼(ウス)で搗いたお餅が食べたい。
皆さんが大豆を一生懸命潰している間に、セイロで蒸して、
ホームベーカリーでついた餅です。
色々な食材を入れて作ることもできます。
その生ぬかをフライパンで炒って「炒りぬか」にして、
粗糖を少量加えたものを一緒にお出したところ…

\まるできなこ餅!/
子供たちも美味しそうに食べていました。
私自身、はじめて「ぬかきなこ」を頂いた時は衝撃でした。笑
それまで「ぬかはぬか漬けにするもの」と、勝手に決め込んでいましたし (;・∀・)
わが家では、毎日食べる分を精米してご飯を炊いています。
餅も同じく、玄米で購入したもち米を精米して食べています。

「炒りぬかきなこ」も美味しいんですが、もっと、ぬかをより美味しく食べることができないか、考えていたら…

パパ「アルファー化したらいいんじゃない?」
と、提案が。
アルファー化?
理系パパによる説明が10分ほど続きました。
要するに、一度、水を含ませて炊いた後で、急速に熱乾燥することで、
✔ 甘味が増す
✔ 保存性が高まる
とのこと。
いいこと尽くめじゃないですか (;”∀”)
早速パパ考案のレシピで作ってみます。
まずは、精米したぬか(今回はもち米)とその3倍くらいの水を入れて
ぐつぐつと炊いて「ぬか煮」にします。

フツフツとしてきてから、2、3分で火を止めます。

そして、予熱150℃で温めておいたオーブンで、
このアツアツの「ヌカ煮」を乾燥させます。
まんべんなく乾燥するよう、途中スプーンなどを使って
ぬかをかき混ぜ、平らにならします。

トータル1時間ほど加熱しました。
乾いたぬかを取り出し、粗熱が取れたら
ミキサーで粉末にします。
ミルサーがないわが家では、ミキサーで代用しています。

まだ少ししっとりしているところが残っていたので、
さらに10分オーブンで熱乾燥しました。
再びミキサーにかけると…

サラサラ~♪
\パウダー状のぬかになりました!/
早速、「豆乳ヨーグルトとアルファー化ぬか」の組み合わせで食べてみることに。

う~ん!
\これは結構いけます ( *´艸`)/
炒りぬかよりも、甘味を感じるので、よりきなこに近い味です。
ちなみにわが家の子供たちは、砂糖やハチミツなどの甘味を足さずにそのまま食べています。
✔ ぬかの栄養を丸ごと摂りたい
✔ ぬか漬け以外の使い方を探している
✔ 大豆アレルギーがあって、きなこを食べられない
そんな方におすすめです♪
アルファー化ぬか、色々な料理に使ってみようと思います (=゚ω゚)ノ
もちろん、アルファー化しないで、ぬか漬けという選択肢も!
生ぬかは、自然食品のお店などで購入することもできます。
やはり1番フレッシュなのは、精米したての生ぬかです。
✔ 玄米を購入し、使う直前に精米する
がおすすめです。
わが家で使っている精米機は、お米屋さんの本格精米ができる「圧力式」の精米機。

家庭用の主流は「かくはん式」ですが、お米が欠けにくい圧力式を選びました。
ご飯も、白米→7部づき→5部づきと徐々に精米歩合を変えていき、
今は「3部づき」を食べています。

8年ほど前に購入しましたが、ほぼ毎日お世話になっています。笑
精米機おすすめを探してみました。
ぬかも美味しくいただくコツは、「農薬化学肥料不使用」や「特別栽培認証」の玄米を選ぶこと!
食べチョクは、農薬の基準がしっかりしているから、安心して購入できるのが嬉しい♪

youtubeに、『nanairo!チャンネル』ができました!
まだまだ動画は少ないですが、
自家製の発酵食品の作り方や、それを使ったレシピを公開していく予定です。