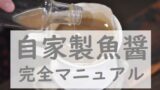自家製の調味料やら保存食やら、所狭しと並んでいるわが家をみて、
「作れないものなさそうですね。」って言われることがよくある。
「何でも作れますよ!」と言いたいところだが、残念なことに、
頑張っても作れないものは意外に多い。
その一つが、石川県に伝わる『ふぐの子』。
猛毒のテトロドトキシンが含まれているふぐの卵巣を、3年もの間塩漬けにし、
無毒化したものを米糠に漬け、さらに酒粕に漬ける。
製造には許可が必要で、出荷の際にはネズミによるサンプルチェックが行われるという、
気が遠くなるほど手間の掛かった、禁断の珍味。
15年くらい前に、一度だけ食べたことがある。
「毒は残ってないよ。」って言われても、妙に緊張してしまい、
味はほとんど覚えていない。
一応一緒に食べた主人に確認してみたところ、
「えっ?美味しい美味しいって、あっという間に食べ切ってたよ。」だって。
なるほど、相当好みのタイプだったことは確か。
ふぐの卵巣は諦めても、あの味は諦め切れない。
食べたことすらうっかり忘れそうだった私とは対照的に、探究心のかたまりのような主人は、
いつか作ってみようって思い続けていたらしい。
さすがに一般人である主人が、ふぐの卵巣に手は出せない。
使う魚卵は、わが家でお馴染み『マダラの卵』。
それなりの大きさで食べ応えがあり、それでいて価格は控えめ。
冬の時期に限られるが、スーパーでも手に入るお手軽食材。
イクラでもない、スケトウラダのタラコでもない、
謎多き卵を買ってみようなんて人はあまりいないようで、割引シールが貼られるまで残っていることも多い。
そんなマダラの卵は、二つの卵巣がくっついた状態=一腹で売られている。
大きさにこだわるより、まずは破れのないきれいな状態のものを選ぶのがおすすめ。
いいマダラの卵が手に入ったら、夜な夜なせっせと仕込み開始。
工程は「塩漬け」「糠漬け」「粕漬け」の3つ。
ひたすら漬ける、そして待つ。
まずは塩漬け。
塩に漬ける目的は、魚卵から余計な水分を抜くこと。
全体が覆われるほどの、大量の塩を使う。
大体魚卵の20%。
海で採れた食材を使う時は、海の塩を使う。
表面の皮が顏を出すと、腐敗の原因にもなるので、
ピンポイントで追い塩をする。
最初の3日くらいは、驚くほど水が出るので、
深めの容器で漬けておくと安心。
出てきた水はその都度捨て、1週間塩漬けの状態を保つ。
涼しいところで保管できるのであれば、特に冷蔵庫に入れる必要はない。
それに皮が破れて中の卵が出てこなければいいので、いくつか重ねて(3~4個)漬けてOK。
1週間経って、全体がカチカチと引き締まった状態になっていれば、
塩漬けの工程は完了。
次は糠漬け。
味を決める重要な工程、漬ける糠もただの糠ではない。
きちんと配合したぬか床が必要。
材料は、米糠、魚醤、みりん粕、米麹(糀)、鷹の爪、山椒の実。
魚醤は、イワシの魚醤がおすすめ。
自家製の魚醤があったらベストだが、魚醤から作ろうと思ったら半年は掛かる。
迷ったら地のものを合わせるとしっくりくる。
ということで、同じ石川県に『いしる』という魚醤があるので、
今回はそれを使ってみるのがよさそう。
次にまぼろしの発酵食品ともいわれる、みりん粕。
都内近郊だと、千葉の流山に「かごや商店」という酒屋さんがあって、
そこに行くと、ほとんど通年で購入できる。(オンラインショップもある。)
予約必須の流山本みりん、その搾り粕というだけあって、
そのまま食べても抜群に美味しい。
今まで試したみりん粕の中では、1、2位を争うしっとり感。
長期間漬けると、どうしても水分が抜けていってしまうので、
みりん残量率高めの、しっとりしたみりん粕がおすすめ。
もしみりん粕が手に入らなかったら、本みりんで代用することも可能だが、
漬け終わった粕まで美味しく食べたいわが家としては、わざわざ買いに行ってでも、
みりん粕を使いたい。
米麹は、乾燥麹ではなく、生の麹がおすすめ。
冷凍すると半年くらいは保存できるので、まとめて買っておくと便利。
味噌だけではなく、甘酒や醤油麹、三五八漬けなど色々作っていると、
あっという間になくなる。
これら全ての材料を混ぜ合わせ、ツボ型の深めの容器に、
ぬか床、魚卵、ぬか床、魚卵…と交互に入れていって、上から重石をする。
ぬか床に漬ける期間は、およそ6か月。
木樽で漬けると水分が抜けやすいので、陶器や塩分に強いプラスチックの容器がおすすめ。
慣れるまでは、プラスチックの容器に漬物袋を入れて、
その中で仕込むと、空気も抜きやすい。
そう、麹は嫌気性発酵なので、空気が苦手。
かといって、完全に密封してしまうと、
自ら発生させる微量のガスによって、数日で腐ってしまう。
ほどほどが一番。
重石をしたまま6か月、表面はカチカチのままだが、
ぬかの旨味をまとった熟成卵ができあがる。
ここまでで、ほぼ『へしこ』と同じ状態。
今回は、そのへしこをさらに粕漬けにする。
日本酒の搾り粕、酒粕。
大吟醸、吟醸、清酒と色々あるが、わが家では、
風味と味のバランスのよい、吟醸酒粕を使っている。
ぬかを軽く落としてから、吟醸酒粕に漬ける。
夏になって暑くなってくると、産膜酵母が発生しやすくなるので、
表面を軽くビニールで覆っておく。
実は2週間程であげるつもりが、うっかり忘れて6か月…
最悪食べられない事態を予測して、おそろおそる開けてみたら、
なんとも芳醇な香りがしてきて、期待値が一気に跳ね上がる。
白かった酒粕は飴色になり、カチカチだった魚卵もほろっと崩れやすくなっている。
旨味がギュッと詰まった卵が美味しいのはもちろん、まわりの粕との相性がこれまたバツグン。
小瓶に上品が量が入って2千円!って、法外な値段で並んでいたとしても、
その味を知っていたら買ってしまうかも…ってくらい、想像をはるかに超える美味しさ。
発酵生活はじめて10年、わが家史上最高の珍味であることは間違いない。
とにかく作って損はない。
あまりに美味しくて、あっという間に食べ切ってしまい、
写真を取り忘れるという大失態…
次のシーズン(2025年12月頃)に、写真付きで詳しいレシピを公開予定。
気になって眠れない方は、サイドバーにある『購読』ボタンを。
『ふぐの子』、酒飲みじゃなくても一度は食べたい禁断のグルメ。
実際「あっ、これ気になってたんだよね!」って、贈って喜んで貰えることも多い。
お中元、お歳暮、内祝など、わが家の定番の贈り物になりつつある。
商品の詳しい内容やお取り寄せはこちらから→いつもお世話になっている本場北陸の老舗、『荒忠商店』