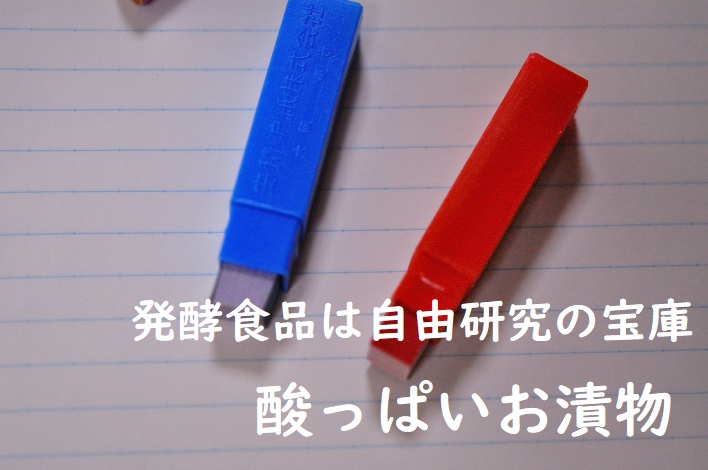毎年7月になると、小学生がいる家庭では、
なぜかそわそわ落ち着かない日々。
その先に待ち構える夏休みをどう乗り切るか、気が気ではない。
まずは毎日のお昼ご飯問題。
後片付けをしたと思ったら、もう次のご飯作り。
母に夏休みはない。
それに外はうだるような暑さ、気軽に公園で遊べやしない。
ジワジワ値上がりする電気代も気にはなるが、背に腹は代えられない。
大人も子供も、クーラーの効いた家でゴ~ロゴロ。
そして一番頭を悩ませるのが、夏休み恒例の宿題たち。
ワークはさっと終わらせたとしても、読書感想文と自由研究だけはそうはいかない。
子供の宿題といいながら、放ったらかしにしていたら、
眠い目をこすりながら、夜な夜な親子でまとめ作業、、
なんて最悪な最終日を迎えることにもなりかねない。
わが家にも現役小学生(次女)がいる。
本好きの彼女にとって、読書感想文は、
出来はどうあれ、ストレスフリー。
本屋さんでお気に入りの一冊を選ぶ特典まで付いてくるなんて、なんてラッキー!って思ってる。
となると、問題なのは自由研究。
「何がいいかな?何がいいと思う?」って、やる気は十分。
発酵食品は自由研究の宝庫
数えてみたら、これまで15以上の実験をしてきたわが家。
定番の『生き物の観察』や『植物の成長日記』も目線を変えれば面白いが、
理科の授業の延長のような感じだと、どうもテンションが上がらないらしい。
そこで目を付けたのが、『発酵食品』。
理科の要素と家庭科の要素、どちらもバランスよく入っている。
時間を掛けて変化していく発酵は、地味ではあるが面白い。
腐敗と違うとはいえ、その差は紙一重だったりもする。
カビなの?産膜酵母なの?
食べられるの?食べられないの?
視覚、嗅覚、味覚、すべてを使って、
自分で判断しなければいけない。
どこにも賞味期限は書いていない。
昔から作り続けられている、伝統的な発酵食品作りがおすすめな理由
✔特別な道具を使わない
✔材料は身近な食材、子供が扱えないような危険な薬剤は使わない
✔基本は混ぜて待つだけ、工程がシンプルなものが多い
大人に頼らずとも、子供だけでも進めることができる。
ただし、一つだけ注意が必要。
発酵食品の中でも、味噌ように出来上がりまでに1年以上掛かりますってものや、
豆板醤のように、夏に入手するのが難しい旬の食材を使うものは、
自由研究には向かない。
あくまで夏休みの期間、まとめる時間も考慮すると、
長くても1ヶ月で結論が出る実験がいい。
そこで一番おすすめの発酵食品が、『しば漬け』。
千枚漬け、すぐき漬けと並び、京都三大漬物の一つに数えられるしば漬け、
その起源は、平安時代にまでさかのぼる。
これぞ京の味とされる、由緒正しきお漬物。
夏野菜の代表選手の茄子と大原の赤紫蘇、それを塩だけを使って乳酸発酵させる。
絶妙な酸味で、夏バテしがちな時期でも、不思議と箸がすすむ。
酢を入れて酸味を出している、なんちゃってしば漬けとは一線を画す。
(それもそれで美味しいけど…)
わが家も毎年作り続け、そろそろ10年、
夏の時期しか作れないこともあり、好みの味にするのに、
5年以上の歳月を費やした。

しば漬けは、上で挙げたの自由研究の必須要件にピタリと当てはまる。
✔特別な道具を使わない
→使う道具は、包丁まな板とボウルと量り、それと温度計とリトマス試験紙
(リトマス試験紙は、買おう。)
✔材料は身近な食材、子供が扱えないような危険な薬剤は使わない
→材料は、茄子と赤紫蘇と塩だけ
✔基本は混ぜて待つだけ、工程がシンプルなものが多い
→野菜を切って、塩を加えて混ぜるだけ
水分がしっかり出れば、あとは発酵が進むのを待つだけ。
自由研究で大事なのは、変数を増やし過ぎないこと。
変数が多いと、結論がぼやける。
なので、要素は2つ、多くても3つまで。
塩の量を2パターン、温度を3パターンにすると、
2×3で6つの答えが出てくる。
塩分量は2パターン。
ザワークラウトと同じ2~3%と、漬物としてはギリギリ食べられるくらいの7%。
温度は3パターン。
クーラーの効いた室温、冷蔵庫の中、それと30度超えの屋外。
この6パターンを調べ、味や見た目を比べながら、
ベストオブしば漬けを作る。

実際わが家でもやったことがあるが、結論がすぐに出るものもあれば、
一番美味しい時期はいつか、出来上がりのタイミングを迷うものもある。
ちなみに、賞を受賞しているような自由研究をいくつか読んで分かったのは、
答えは必ずしも正解でなくてもいい、ということ。
常識とか、当たり前とか、そういうのに当てはめていくものではなく、
小学生がその実験で分かったことを、自分の考えと共にまとめていけばそれで十分。
大人が答えを用意して、そこに導く必要もない。
それが分かれば、保護者も一気に楽になる。
さてさて、本場大原でも、
7月から8月中旬お盆くらいまでが赤紫蘇の最盛期。
今年は迷わずしば漬け作りにチャレンジしよう!